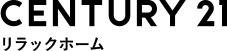SOUZOKU
【相続】親から受け継いだ不動産でお困りなら
不動産は現金などと違って簡単に動かすことができず、資産価値もかなり高いものです。また、相続するためには手続きもあるため、知識がないと難しく感じられてしまうことでしょう。そのため、「まず何から手続きすればいいのかわからない」「相続時にかかる税金や費用が心配」という方も少なくありません。
ここでは名古屋市で不動産売却を対応している「リラックホーム」が不動産を相続した時に行うこと・流れや、相続時にかかるお金について解説します。
こんなお悩みありませんか? Souzoku
- 不動産を相続したが、何をすればいいの?
- 不動産の相続・・・いつか来るけど、来たとき大丈夫か。
- 「いざ」となった時の為に知識を得ておきたい
- 不動産を相続した時の税金っていくらかかるの
- 相続した不動産で親戚ともめたくない
不動産の所有者が亡くなってから行うこと Souzoku
-
1相続の発生
被相続人が亡くなったことがわかった時点から相続が発生します。まずは親族に連絡し、葬儀の準備を進めます。また、被相続人が親しくしていた方など関係者への連絡を行います。
葬儀にかかった領収書の整理・保管も忘れずに行いましょう。 -
被相続人が入っていた健康保険や厚生年金保険の資格喪失手続きを行います。相続発生から5日以内に行いましょう。
-
3死亡届と火葬許可申請書の提出
(7日以内)被相続人の死亡から7日以内に各市区町村に死亡届および火葬許可申請書を提出します。死亡届には医師からもらった死亡診断書を添付しましょう。形見分けを行う場合は初七日の法要で済ませるのが一般的です。
-
国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金は14日以内に資格喪失手続きを終えるようにします。
-
5遺産の調査と相続人の確定
(3か月以内でできる限り早く)被相続人が残した遺産の調査と相続人の確認を行います。相続を承認・放棄の意思表示は3ヶ月内であるため、その期間内にできる限り早く進めましょう。
遺産は現金や不動産はもちろん、借入金も含みます。それらを調査し、相続人をはっきりさせた上で相続するかどうかを決めます。
遺言書がある場合はその内容に従って相続人や分配割合が決定されます。 -
相続発生から4か月以内に所得税の準確定申告を済ませておきましょう。
-
7遺産分割協議書の作成
(10か月以内)相続税は相続発生から10か月以内に納税する必要があります。そのため、遺産分割協議もそれまでに終わらせなくてはいけません。協議内容に従って遺産分割協議書を作成しましょう。
-
埋葬料・葬祭費・高額療養費・高額介護合算療養費を各自治体に申請します。国民年金の死亡一時金の請求も2年以内に行いましょう。
-
9死亡保険請求(3年以内)
死亡保険は3年が時効となります。そのため、この期間内に必ず請求するようにしておきましょう。
-
国民年金の遺族基礎年金・寡婦年金、厚生年金の遺族厚生年金の支給を申請します。また、国民年金・厚生年金の未支給分も請求しておきましょう。
不動産相続にかかる費用一覧表 Souzoku

遺産の中に不動産がある場合、それを相続するためには手続きが必要なことはもちろん、さまざまな費用・税金もかかります。たとえば相続登記に必要な登録免許税、相続人同士で取り決めた内容がまとまっている遺産分割協議書の作成費用などです。また、相続手続きは複雑で面倒なことも多いため司法書士に依頼するのが一般的で、それに依頼料もかかります。さらに、被相続人が遺言書を残す場合はその作成費も必要です。
このように、不動産相続ではさまざまな費用・税金がかかります。具体的にどのようなお金がかかるのか、表でまとめましたのでご覧ください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 内容 | 金額の目安 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 相続登記をする際に必要な税金です。 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 必要書類の取得費用 | 戸籍謄本や住民票など各自治体で必要な書類を取得する際に必要な費用です。 | 1通で数百円程度 |
| 遺産分割協議書の作成費用 | 行政書士や司法書士などの専門家に遺産分割協議書を作成依頼する際に支払う費用です。 | 遺産総額×0.3~1% |
| 司法書士への登記手数料 | 相続登記の手続きを依頼する際にかかります。 | 6~7万円前後 |
| 遺言書の作成費 | 被相続人が公正証書遺言を作成する際にかかる費用です。 | 財産の評価額によって変動する |
親族同士のもめごとや、なくなる前の事前準備

残念なことに、相続をきっかけに親族同士の仲が悪くなってしまうケースが後を絶ちません。
相続人が全員納得していれば問題はありませんが、家や土地は誰が相続するのか、相続する財産は平等に分けられるのか、といった問題が絡むと、話がこじれてしまい、親族間に大きな亀裂を生んでしまうのです。
相続に関するもめごと、いわゆる「争族」を避けるためにも、元気なうちに財産がどのくらいあるのかを把握して相続について話し合っておくこと、そして遺言書を作成しておくことをおすすめします。
リラックホームは不動産のプロフェッショナルであり、相続についても豊富な知識と経験があります。しっかりサポートいたしますので、相続のお悩み解決は弊社にお任せください。